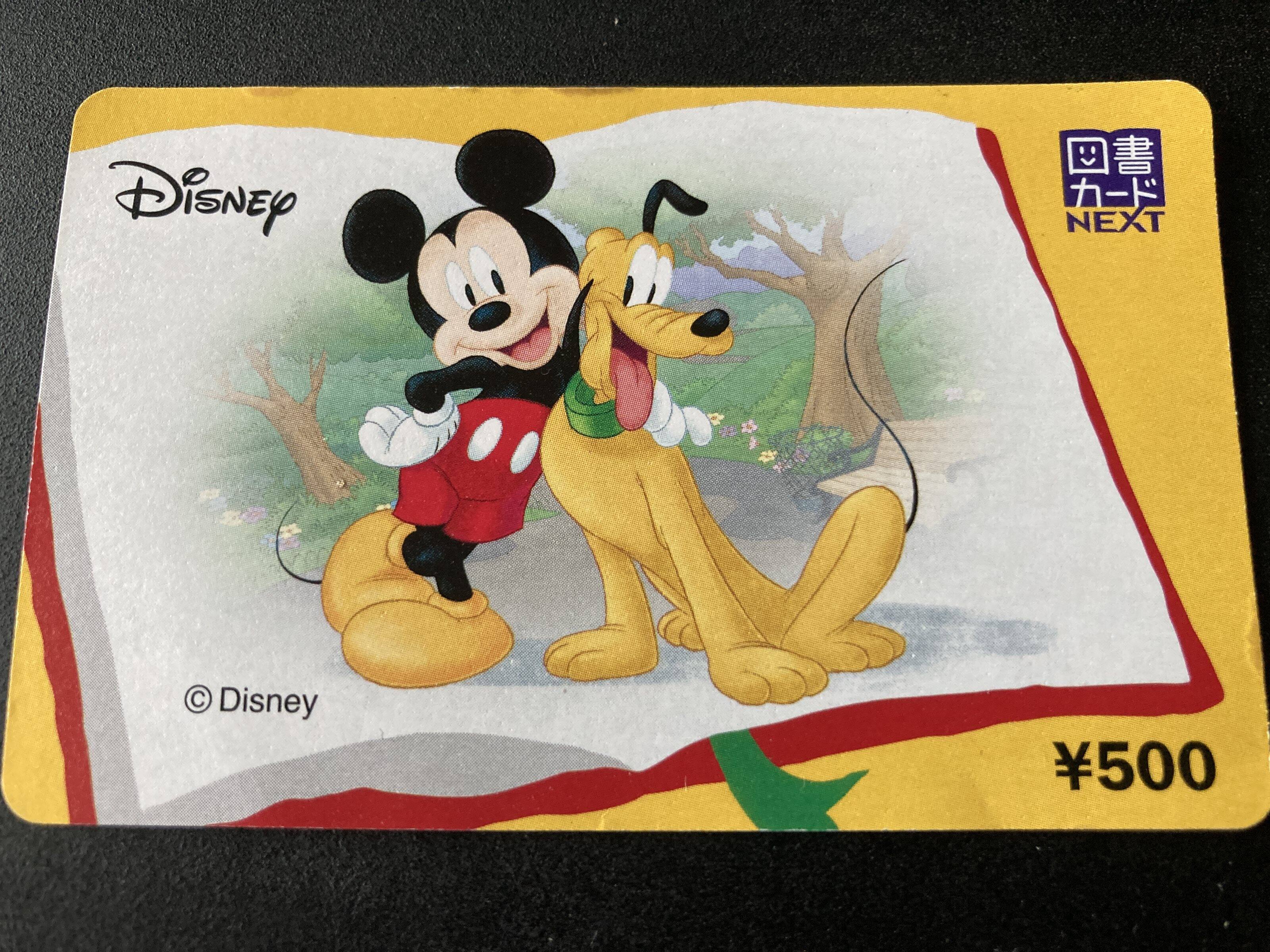
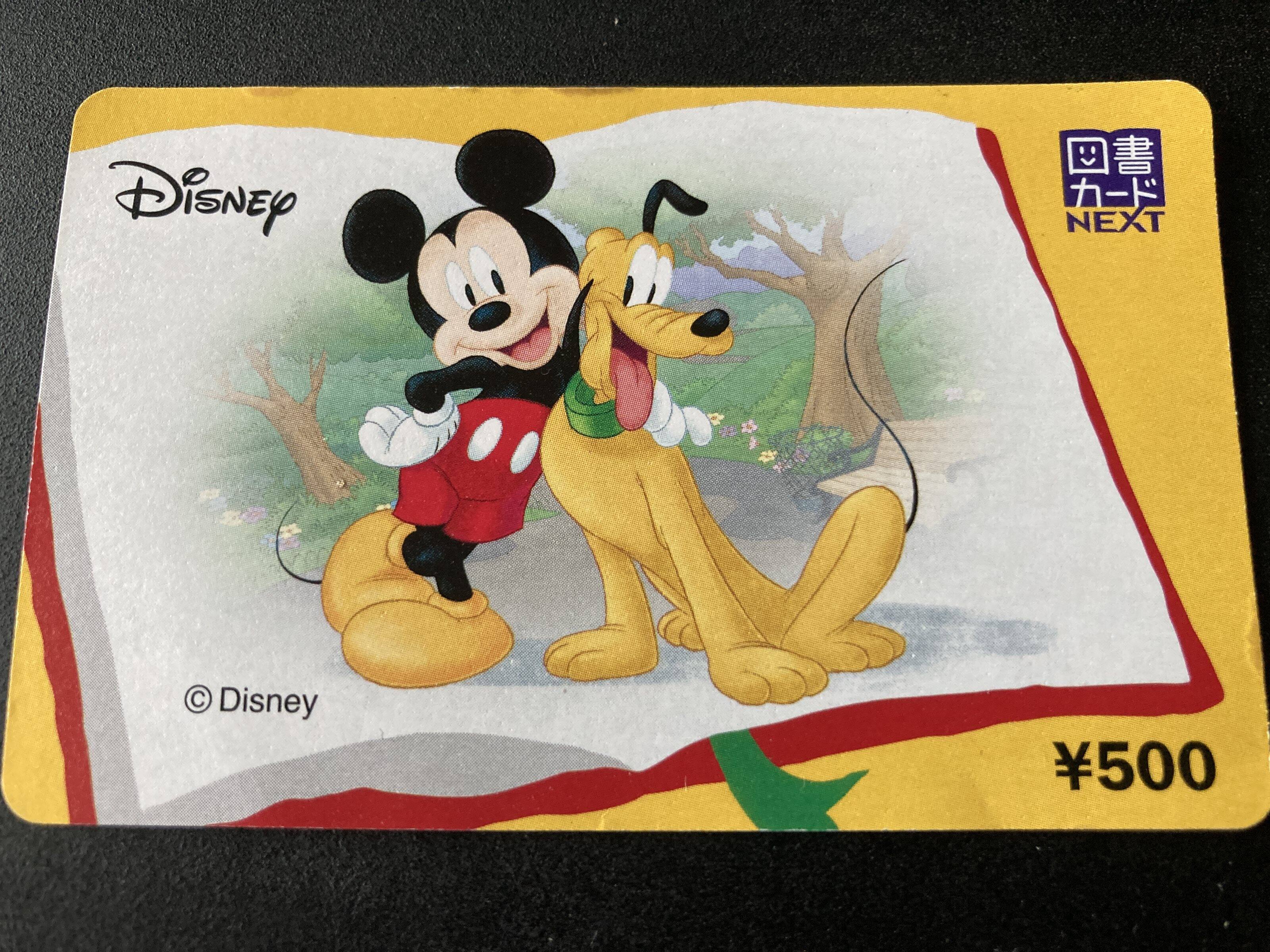
【本好き必見!】金券ショップの図書カードで賢く節約する方法
※本ページのヘッダー写真は筆者撮影

元店長シバ:
いやぁ、シバですわ。 読書、楽しんでやすか?
私ぁね、サクッと読む本はキンドル(電子書籍)、何度も読み返す本は紙と、使い分けていやす。 紙の本を買う時、あなたが真っ先に思い浮かべる節約術は、やっぱり図書カードじゃありやせんか?
元店長シバ:
ですが、この図書カード、昔と今では、事情が全く違っていやす。 元金券ショップ店長として、そのプロしか知らないカラクリ(本音)を、今日は暴露しやす。
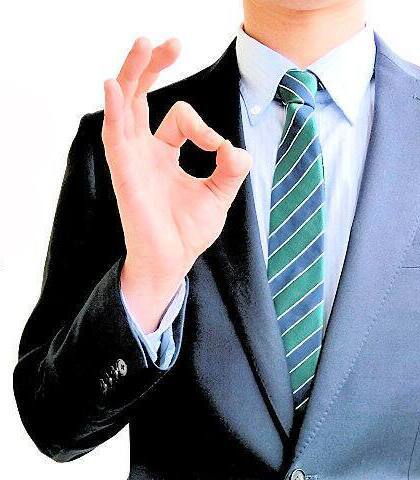
【元店長の本音】なぜ図書カードNEXTは嫌われるのか?
元店長シバ:
図書カードと言やあ、昔は紙の図書券でした。 それが磁気カードになり、今はQRコードを読み取るタイプの図書カードNEXTが主流ですわね。
元店長シバ:
このNEXT、あなた(読者)にとっては便利になったかもしれやせん。 ですが、私ら金券ショップにとっては、とんでもねぇ厄介者になっちまったんですわ。
あなた:
え? なんでですかい? 同じ金券でしょう?
元店長シバ:
甘い! 昔の磁気カードは、使えば穴が開きやした。 穴が開いてなきゃ=未使用(残高アリ)と、一目で判断できた。
元店長シバ:
だが、今の図書カードNEXTはどうです? QRコードですから、使ったか使ってないか、見た目じゃ一切分からねぇんです。
あなた:
裏にスクラッチ(PIN番号)があるじゃないですかい?
元店長シバ:
そのスクラッチが曲者(くせもの)なんですわ! スクラッチが削れていようがいまいが、残高があるか無いか、店では確認できねぇんです。
金券ショップには、本屋さんみてぇな残高確認の端末がねぇですから。
元店長シバ:
じゃあ、どうやって確認するか? 私らプロは、お客さんから買い取った後、 1枚1枚、裏のスクラッチを削り、 パソコンで専用サイトを開き、ID番号とPIN番号を手打ちして… と、とんでもねぇ手間と時間がかかるようになっちまった!
元店長シバ:
500円のカードを100枚も持ち込まれた日には、もう仕事になりやせん(苦笑)。 利益よりも手間(人件費)が上回っちまう。
だから、大手の金券ショップほど、この図書カードNEXTの買取をやめちまうか、買取率を大幅に下げて、防衛してるんですわ。
これが、今の現場のリアルな本音です。
【元店長の体験談】高額の図書カードは誰が買うのか?
元店長シバ:
じゃあ、図書カードなんざ、もう価値がねぇのか? いえいえ、そんなこたぁありやせん。
金券ショップの店頭では、今も人気ですわ。
(※買う時は、プロが手間をかけて残高確認を済ませたものを売ってやすから、安心してくだせぇ)
元店長シバ:
私がお店をやってた頃、 10,000円や5,000円の高額な図書カードがよく売れたのを覚えていやす。
誰が買うのか? プレゼントも多いですが、意外なのが、お医者さんですわ。
元店長シバ:
勉強のために、医学の高けぇ専門書を何冊も買うから、少しでも安くしたいと。 9,800円で10,000円分の図書カードを買って、 200円を浮かせ、その200円を積み重ねている。
こうやって節約してるんですわ。
【プロの節約術】Amazonルートは死んだのか?
元店長シバ:
本好きの節約術として、昔は最強の裏ワザがありやした。
金券ショップでAmazonギフト券を安く買う ↓ そのギフト券でAmazonで図書カードを買う
…という二重取りの錬金術です。
元店長シバ:
ですが、残念ながら、この黄金ルートは、今は死にやした。 Amazonが規約を変えちまってね。ギフト券で図書カードは買えなくなっちまったんです。
元店長シバ:
じゃあ、もう金券ショップは無意味か? いいや、まだ手はありやす。
ブックオフ(BOOKOFF)ですわ。 ブックオフは、中古だけじゃなく、新刊も売ってやすよね? 店舗によっちゃあ、図書カード(NEXT)で中古本も新刊も両方買えるんです。
金券ショップで安く買った図書カードで、 ただでさえ安い中古本を買う。
これぞ、今に残された、最強の節約術ですわ。
(※使える店舗と使えねぇ店舗がありやすから、必ずレジで確認してくだせぇよ!)
【元店長シバの結論】金券ショップより「確実に得する」方法
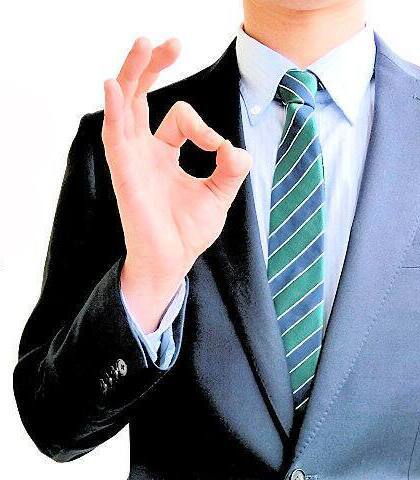
「最後まで読んでくれて感謝します。ぶっちゃけ言いますと、10円安いチケットを探して店を回るより、支払いを全て『高還元クレカ』に変える方が、年間3万円以上も節約できますわ。」
私が現役時代、本当にお金が貯まるお客様は皆、現金ではなくこのカードを使っていました。
- 店に行く「時間」と「電車賃」が浮く
- 電気・ガス・携帯代も勝手に「割引」になる
- 年会費無料だから、損するリスクはゼロ
※元店長シバの「クレジットカード研究室」へ移動します















